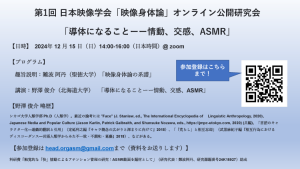中部支部では、下記の通り中部支部 第2回研究会をオンライン(Zoom)にて開催いたします。
中部支部会員に限らず多くの方の参加をお待ちしています。
中部支部会員以外の方は事前登録をお願いしております。
参加希望の方は下記リンク(Googleフォーム)にて事前申し込みをお願いします。
申し込み締め切りは12月12日(木)、研究会前日にZoomリンクをメールにてお知らせいたします。
https://forms.gle/jp1Bt4eS1w3nmQPb9
+++++++++++++++++++++++
2024年度 | 日本映像学会 中部支部 | 第2回研究会
日時:2024年12月15日(日)(13:30 開始)
会場:オンライン(Zoom)
担当校:静岡文化芸術大学
◎研究会スケジュール(予定)
13:20 – 第2回研究会 受付開始
13:30 – 開会あいさつ
13:35 – 14:35 研究発表(2件)
休憩
14:50 – 15:50 招待講演(1件)
15:50 – 16:20 ディスカッション
16:20 – 閉会あいさつ
◎招待講演(トークイベント形式)
横断型アートアニメーション作家・榊原澄人
要旨:
榊原氏は1990年代後半から、ビデオ、インスタレーション、アニメーション作品などを幅広く制作してきた。彼の作品は具象的でありながらも、従来の意味での物語性は持たず、「時間の圧縮」「モーションの反復」「モチーフの変転」「原画と動画」といったアニメーションの特性を、媒体の命題として掲げている。また、その活動は短編映像作品にとどまらず、フリップブックとキネティック・アートを組み合わせた最新作では、彫刻的要素も取り入れられ、アートとアニメーションの境界を横断する新たな表現が試みられている。
本講演では、静岡文化芸術大学のブルベス・ジェローム氏を聞き手として、榊原氏のこれまでの作品とその創作過程、そしてアニメーションと現代美術の境界を行き来する創作活動についてお話しいただく。
ゲスト紹介:
榊原 澄人(さかきばら すみと)
1980年 北海道十勝生まれ。15歳で渡英後、2003年文化庁芸術家海外派遣生として英国王立美術大学院(Royal College of Art)アニメーション科修士課程を修了。 長野県北信山麓在住。国内では、文化庁メディア芸術祭大賞受賞作品「浮楼」、DOMANI展(2015)にて注目を浴びた「É IN MOTION No.2」、スパイラル30周年記念展「スペクトラム」で発表された「Solitarium」をはじめとするアニメーション映像作品で知られ、美術館やギャラリー展示など現代美術の文脈でも活動を広げる作家。2021年長野県立美術館改装後初のこけらおとしの展覧会として発表された作品『飯縄縁日』は26mのパノラマ投影インスタレーションとして現在も常設展示されている。
◎研究発表(2件)
「当事者」から考えるクィア映画上映空間
和田 栄美 (名古屋大学大学院人文学研究科映像学分野・専門 |博士前期課程1年)
要旨:
クィア理論とアイデンティティポリティクスの間に存在する「クィアジレンマ」や、英語圏のクィア理論をどの程度まで日本社会のクィア的実践を考える上で参照すべきかに関しては、様々な議論が展開されてきた。本発表では、日本語特有の「当事者」という言葉をキーワードに、「セクシャルマイノリティ当事者」を脱構築に解釈する場としてクィア映画上映空間を捉え直し、その空間から派生するネットワークや親密圏の形成について考察する。
『コンフィデンスマンJP』に見るポストフェミニズム:新自由主義経済とフロネシス
渡邉 ゆき(オタゴ大学人文学部 メディア・フィルム・コミュニケーション学科|講師)
要旨:
本発表は、ポストフェミニズムの見地から最近の映画三部作『コンフィデンスマンJP』(2018年、2020年、2022年)の女性主人公像を検証する。詐欺師3人組のリーダーであるダー子(長澤まさみ)は、「フロネシス」(Kupfer, 2023)の概念を体現する実践的な知恵を駆使し、国内外の悪徳詐欺師やマフィアから大金を奪いながら、バブル時代のような派手な生活を楽しむ。戦中戦後の男性中心社会が築いた日本の国際的地位が衰退する中、この女性像を通して、新自由主義経済とその歪みの中で生まれた女性への期待と不安を考察する。
◎補足情報
日本映像学会中部支部 幹事会
※幹事メンバーのみ
会場:オンライン(Zoom)
時間:12:30 – 13:00
2024年度 | 日本映像学会 中部支部 | 第2回研究会
————————————————————————
研究会は学会員でない方も聴講可能です。
興味がありそうな方に、お知らせいただければ幸いです。
ただし、今回はオンライン開催のため、中部支部会員以外の方は事前登録をお願いしております。下記より事前に登録いただくようにご案内ください。
https://forms.gle/jp1Bt4eS1w3nmQPb9
以上、よろしくお願いします。
+++++++++++++++++++++++
日本映像学会 中部支部事務局
email: msaito nuas.ac.jp (齋藤)
nuas.ac.jp (齋藤)